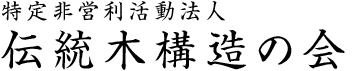第4回 伝統木構造の会 秋季セミナー in鶴岡のレポート
10月11日のプレイベントを含めた
伝統木構造の会の第4回秋季セミナーが鶴岡を舞台に行われました。
セミナーのスケジュールは下記の通りでした。
■2008年10月11日(土)
【新潟見学会】
「マサカリ・チョウナ加工の実演と現代民家づくり見学会」
斑鳩建築作業場 (新発田市真野原) と住宅、保育園、納骨堂の見学会
その後 削ろう会懇親会
■2008年10月12日(日)
【鶴岡秋季セミナー1日目】
三川町立東郷小学校へ
増田一眞 伝統木構造の会 会長挨拶
パネルディスカッション [Ⅰ]
「三川町立東郷小学校の建設の経緯と鶴岡の木材供給」
司会:劔持猛雄棟梁(大工会幹事長)
パネラー
菊間満(山形大学教授)
菅原英介(建築家)
パネルディスカッション [Ⅱ]
「伝統木構造を現代に生かす知恵」
*パネラー
司会:菊地均棟梁(大工会副会長・茨城)
パネラー:直井光男棟梁(大工会会長・福井)
海老崎粂次棟梁(大工会副会長・山口)
大屋好成棟梁(千葉)
小川正樹棟梁(新潟)
小川三夫棟梁(栃木)
劔持猛雄棟梁(山形)
白根伸浩棟梁(埼玉)
田中健太郎棟梁(富山)
富樫純治棟梁(山形)
三浦保男棟梁(長野)他
懇親会
■2008年10月13日(月・祝)
【鶴岡秋季セミナー2日目】
「大工技術講座」 大工会会長 直井光男 棟梁
本陣 前庭にて 「直井棟梁直伝、大工実技講習」
本陣脇 築山にて 「芋煮会」
その様子をリポートにまとめていただきましたので掲載します。
さて、リポートは会員の越智隆浩さんです。
まずは越智さんの報告の触りから。
詳しくは、行末の書類をダウンロードして下さい。
今回スタッフをしながら鶴岡セミナーに参加しました。
事務局野木さんより、セミナー報告書を書いてほしいとの依頼で
したので、簡単ですが書かせていただきました。
添付ファイルをご覧下さい。本当に簡単なメモ程度の文章で申し訳
ないですが・・・。
081011in_turuoka.pdfをダウンロード
■『建築史講座』-何のために建築史を学ぶのか-のご案内
《伝統木構造の会 主催行事》
『建築史講座』-何のために建築史を学ぶのか-
※掲載情報の赤文字箇所を訂正しました。2008.10.15
(開始時間にお気を付けください。午後6:30~9:00)
講師:後藤治(工学院大学教授、本会顧問)
平成20年10月開講、毎月1回、連続5回講座
伝統木構造の会では、これまでに、限界耐力計算法などの木構造に関わる連続講習会を開催し、現在は架構学講座が進行中です。構造の理解を深めずに、丈夫で美しい木造建築はできないからですが、質の高い木造建築を実現するには、これ以外にも様々な知識や感性をも身に付ける必要があります。そこで今年度から、会員の総合的なスキルアップに寄与すべく、構造以外の連続講座も企画することといたしました。
その第1弾となるのが、本会顧問の後藤治さんを講師にお招きして開催する「建築史講座」です。講座の前半は、下記内容の建築史になりますが、サブタイトルにあるように、知識的な解説に止まらずに、歴史から学んだことをどう今日に生かすのかといった、建築史の枠を超えた実践的な講義になると思われます。また、後半の町並みや民家の再生においては、実例を挙げながら、どう取り組んだらよいのか、修復の際の注意点などを具体的かつ現実的に解説していただく予定です。この機会に、より多くの皆様の参加を心よりお待ち申し上げます。
□日程・内容 時間はいずれも午後6:30~9:00
1回目 平成20年10月17日(金)木材からみた建築史
2回目 11月14日(金)木造架構の変遷-1
3回目 12月19日(金)木造架構の変遷-2
4回目 平成21年 1月23日(金)町並みの再生
5回目 2月13日(金)伝統民家の再生
□会場 工学院大学新宿校舎(新宿駅西口より徒歩5分)
□講師 後藤治(工学院大学工学部建築都市デザイン学科教授)
□募集人数 60名程度
□参加費 5回連続受講の場合
会員12,500円 非会員15,000円 学生7,500円
1回のみ受講の場合
会員3,000円/回 非会員3,500円/回 学生2,000円/回
□お問い合わせ・お申し込み
特定非営利活動法人伝統木構造の会事務局
東京都渋谷区代々木2-36-6
TEL:03-3370-8528
FAX:03-3375-8447
■受講申込は添付のpdfの用紙をお使いください。
まだ若干の空席があります。お申し込みはお早めに!
『建築史講座』-何のために建築史を学ぶのか
申し込み用紙 -PDF
081017kenchikushi-kouza.pdfをダウンロード
構造見学会のご案内
10月5日に予定しました構造見学会を、
10月18(土)・19(日)日に延期いたしました。
見学を予定された方はご連絡下さい。
この建物は、通し貫構法です。梁組みは大梁と重ね梁を組み合わせ、
建物中心部は差し鴨居で固めています。
現場進行状況は、案内の写真が10月3日現在です。
構造の建て方が終わり、垂木が終了した状態です。
是非ご参加下さい。
信州事務局・三浦
詳しい応募要項は.pdfファイルをダウンロード下さい。miurkenngakukai10.18.pdfをダウンロード
■ちからとかたちを考える<架構学>講座 再募集のご案内
「架構学講座」は、素材の特性や力と形の関係を知り、仕口や継手のメカニズムと加工・組立の工法を学ぶことを主な内容として、昨年9月末に開講しました。7月26日の時点で第20 講目が終了し、約40名の会員が継続的に受講されています。そして、11月からは第3期講座が始まろうとしています。
この架構学講座は、増田会長の並々ならぬ決意のもとにスタートしました。会長曰く、自分の知見の全てを伝えたい。手元にある全ての資料を提供する。同じ内容の講座は二度とできない。さらに、ここから先の講座は1回完結の内容でまとめていくので、連続講座途中からの参加でも大きな支障はない。と述べています。
本会としては、連続講座途中からの新規参加者の便宜のため、希望者には過去の講座での配布資料および講座内容を記録したDVD ビデオを有償にて配布する準備も整えました。そして、再び会員の方にこの講座への参加を呼びかけることといたしました。どうぞ、またと無いこの講座にご参加いただき、ご自身のスキルアップにお役立てください。講座スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
■日程 毎月第2、第4 土曜日に開講 時間は午後2:00~5:00
■内容 これからの講座内容(予定)については、申し込み用紙PDFに添付の予定表をご参照ください。また、過去の講座内容については、講座会場の受付にて閲覧できます。
詳細・申し込み用紙はこちら
080919kakougaku.pdfをダウンロード
■会場 東京製図専門学校15 号館2 階
東京都新宿区百人町1-16-26
(アクセス)JR総武線 大久保駅南口前
JR山手線 新大久保駅から徒歩3分
■講師 増田一眞(増田建築構造事務所・伝統木構造の会会長)
■募集人数 30 名程度(会員限定)
■参加費 (半年12 回分一括)
会員24,000 円(2,000 円/回)
学生12,000 円(1,000 円/回)
2期目途中からの受講を希望される方は、上記、円/回にて清算いたします。また、1回のみの試し受講も受付けています。詳しくは、お問い合わせください。
■申し込み方法
下添の申込用紙にご記入の上、
FAX03- 3375- 8447
まで、お申し込み下さい。(随時受け付けています。)
詳細・申し込み用紙はこちら
080919kakougaku.pdfをダウンロード
■お問い合わせ
特定非営利活動法人 伝統木構造の会事務局
東京都渋谷区代々木2-36-6
TEL:03-3370-8528 FAX:03-3375-8447
■マサカリ・チョウナ加工の実演と現代の民家づくり作品見学会 (新潟見学会)
大工会主催行事
マサカリ・チョウナ加工の実演と現代の民家づくり作品見学会
平成20年10月11日(土)
小川正樹棟梁(斑鳩建築)と村尾欣一先生(新潟職能短大)は30年前からマサカリ・チョウナを使い、地元の素材を使い、百年建ち続ける民家づくりを実践してきました。一軒平均50本の曲り梁を組みあげ、骨組みの美しい伝統木構造を提案してきました。
2001年には「200年生きるこまくさ保育園」をテーマに国産材97パーセントを使用した、金物補強をしない木組みの保育園を建て、2004年キリスト教納骨堂を竣工しました。2001年から「越後にいきる家を創る会」というネットワークを立ち上げ、地元素材・地元技能の活用を通じた地域起こしの運動を進めています。
今回の見学会ではマサカリ加工の実演と住宅、保育園、納骨堂の見学を企画いたしました。
■集合 10月11日(土)
午前10時 斑鳩建築作業場(新潟県新発田市真野原)
10時~14時 斑鳩建築作業場、住宅、保育園、納骨堂見学
(斑鳩建築作業場 新潟県新発田市真野原)
※終了後 削ろう会 懇親会へ
翌日は「秋季セミナーin鶴岡」へぜひご参加ください。
■参加申込
本会主催・秋季セミナーin鶴岡の申込用紙をお使いください。
新潟見学会 詳細はこちら
081011niigata.pdfをダウンロード
申込書は秋期セミナーin鶴岡 のものをご使用ください。
(削ろう会への参加と懇親会(11日夜)の申込みは別〈下記参照〉です。)
—————–新潟見学会ジョイント企画——————
削ろう会「与板大会」のご案内
(主催:削ろう会与板大会実行委員会)
与板町は信濃川左岸に沿い三島丘陵に接し、長岡市の北部に位置し、ほぼ県中央の古い伝統をもつ町です。与板の特産品である打刃物を皆さんに見て頂き、伝統工芸品や匠の技術のすばらしさに触れていただく機会にと思っております。21世紀は本物の時代とも言われており、全国的にも稀な与板の打刃物をぜひこの機会に見て触れてご体感ください。皆様のご参加をお待ちしています。
■「技能の伝承」
台仕込み講習 平鉋 際鉋 溝道具 刃物研ぎ講習 鑿・鉋・鉋裏上げ 古式鍛錬操業 火造り体験 たたら製鐵 丸太はつりの見学と体験
■場所
長岡市与板体育館 新潟県長岡市与板町与板江西乙2430-1
北陸自動車道 中之島・見附インターより約10分
■費用
削ろう会参加費 500円/1日
懇親会費 7,000円
会場の長岡グランドホテルまでの移動はバスが削ろう会会場まで迎えに来ます。
自家用車での移動も可能。
■申込み先
※削ろう会 与板 参加の申し込み先は、
伝統木構造の会とは別になりますのでご注意ください。
詳しくは、こちら
http://www3.ocn.ne.jp/~tac7/kezuroukai.htm
削ろう会与板大会実行委員会事務局
与板町商工会 電話0258-72-2303 FAX 0258-72-3328
※ 翌日10月12日(日)午後から行われる、
秋期セミナーin鶴岡へは、車で約2時間程度です。
宿泊は、各自、宿をご予約ください。