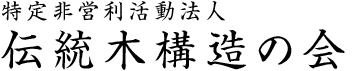『父の日家族ふれあい縁台つくりIN大子』のおしらせ
※伝統木構造の会 会員 菊池均さんより寄せられた情報です。
子ども・いきいき・ふれあい「ぬくもり教室」
『父の日家族ふれあい縁台つくりIN大子』
平成22年6月20日は家族の日(父の日)
家族で座れる縁台を作りませんか。
6月20日は家族の日(父の日)今年も家族で一日のんびりと大子の新緑を浴びながら“家族で楽しむオリジナル縁台”を作りませんか。最近、子供と話しをしていますか。向かい合って話をするのもてれくさいものです。そこで、親子で座れる縁台をつくり、ゆっくりと楽しい会話をしましょう。
いつ 6月20日(日)午前9時から
どこで 茨城県大子町下野宮673 樹輪工場
申し込み先 第23回親父の出番事務局
電話0295-72-2446
〒319-3555 茨城県久慈郡大子町下野宮14了4-3
親父の出番事務局代表 菊池 均
詳細PDF 100620daigoをダウンロード
材料の準備の都合上(親子・家族で先着30組初めての方優先)参加申し込みをお願いいたします。材料はこの日のために1年間あつめておいたものですから参加費は無料です。加工に使う道具は各自準備してください。(のこぎり、げんのう、ノミ、鉛筆)ついでに お母さん手作り弁当。家族での参加をお待ちしております。
終了後、木の文化塾より第23回「親父大将」を決め、記念品を贈呈いたします。
古民家再生セミナーのご案内
※伝統木構造の会友の会会員 稲さんより届いた情報です。
古民家再生セミナーのご案内
この度、利根川源流域の群馬県みなかみ町をフィールドに、奥里山の暮らしや草原の再生に取り組んでいる森林塾「青水(せいすい)」では、下記の通り「古民家再生セミナー」を開催することとなりましたのでご案内いたします。
古民家の様式や構造など基礎的な知識を得ながら、茅葺き古民家や藤原の古民家の状況を視察し、古民家の再生を考えます。古民家に住んでみたい、泊
まってみたい、別荘にしたい、施設として利用したい、古民家づくりをしたい、古民家再生計画に参加したい方など、古民家に興味がある方の参加をお待ちして
います。
詳細はpdfファイルの案内チラシをご覧下さい。
■日 程 7月10 日(土)~11 日(日)
■場 所 □群馬県中之条町
茅葺き古民家や古民家利用の視察
□群馬県中之条町たけやま館
古民家再生プロジェクト概要説明、古民家の構造、デザイン
茅葺き施行方法、古民家再生中の紹介
□群馬県みなかみ町藤原
茅葺き民家、古民家再生事例、藤原地区古民家状況等視察
■参加費 11000円(森林塾青水正会員は10,000 円 、学生会員は7,000 円)
1 泊2食+昼食2食、保険代などを含む
(集合・解散場所までの交通費は各自負担)
■宿 泊 民宿「富士見荘」/群馬県利根郡川場村大字谷地1124
■申込み先 森林塾青水事務局・コミュニティデザイン(浅川潔)/東京都中央区湊1-2-3-301
【電話】 03-6228-3503
【ファクス】03-6228-3504
【メール】 info★commonf.net(★を@に変更して送信してください。)
■古民家再生セミナー案内チラシ こちら
伝木18号
伝木18号
平成22年3月23日発行
■今年を社会に伝統を再認識してもらう年にしよう/増田一眞
■平成二十一年度総会および安曇野セミナー/梅田太一
■伝統構法による建築の修理技術の研修会
安西悦子/廣田文子/真野 晃
■法整備勉強会からの報告/梅澤典雄
■木製建具製作現場見学会/西本直子
■伝統入門2・招き屋根/三浦清史
■木製建具のディテール四/松本昌義
■「伝統の木組競技会」の提案/増田一眞
■総務便り十・ 若者に未来を/井上説子
■ コラム・木の文化と石の文化/稲 貴夫

総会・セミナー/懇親会

地震に耐えた伝統建築

旧岡崎邸の土台と足固め(写真3)
この建物は天保六年(一八三六年)に建てられた鳥取藩の武家屋敷で、昭和十八年(一九四三年)の鳥取地震M七・二が見舞っているがほとんど損傷を受けずに今に至っている。
この建物は現在の木造住宅の基本的構成の原点というべき特徴をもっている。
二階に座敷を設ける二階建住宅。九十センチに及ぶ盤築による地盤改良。
総土台構えで間仕切りにも土台を設ける。
足固を用いて床レベルを固める。五・二寸の面皮の通柱を多用し、二階床を受ける高さに胴差を用いる。二階の軒桁廻りを同一レベルに設置し、小屋梁を架ける。継手は全て金輪継とし、通柱での横架材の仕口にはヤトイ車知を用いる。
これらの合理的な構造計画の考えが短期間でのこの建物の建設を可能にしたと考えられる。また、造作の仕事に関しても、全てに目違・栓・楔を用いた丁寧な仕事で、教科書として採用したい建物でもある。
なおこの建物は現在NPO市民文化財ネットワーク鳥取が寄付金を募りその所有権を確保しその保存に向けて奮闘中である。
更なる皆様のご協力を得られれば幸いである(風)
講習会「伝統を語るまえに・・・・知っておきたい日本の木造建築工法の展開」のご案内
伝統木構造の会では、これまでも木構造に関わる連続講習会を開催し、この程架構学講座が終了しました。続く新規講座として、下山眞司先生を講師にお迎えします。
建物づくりの姿は、地域の環境で異なります。
その環境で暮すなかで、長い年月をかけ、
その地に暮す人びとによって
その地域の環境に適応する建物づくりが考えられてきました。
日本の場合の
環境に適応する建物づくりがどのようなものだったか、
見てみたいと思います。(下山先生談)
木造建築の実例を通し、その清新で溌剌としたつくり手の心を学んで参ります。先生のご厚意により、この度東京での開催が実現しました。長引く不況等、建築に携わる者にとり困難な時でありますが、このような時こそ、心と技を磨く絶好の機会であります。会員・非会員に限らず、より多くの皆様の参加をお待ち申し上げます。
日程・内容 (6回の連続講義です。時間はいずれも15:00〜18:00)
第一回平成22年4月18日(日) はじめに 日本の環境の特徴
第二回 5月16日(日) 日本の木造軸組工法の典型-1、古代の典型:その考え方、
中世の典型1:その考え方
第三回 6月20日(日) 日本の木造軸組工法の典型-2、中世の典型2:その考え方
第四回 7月18日(日) 日本の木造軸組工法の典型-3、近世の典型1:書院造・その考え方、
近世の典型2:武士の住居・その考え方
第五回 8月22日(日) 日本の木造軸組工法の典型-4、近世の典型3:農民、商人の住居・その考え方
まとめ:日本の建物づくりの考え方・・・・それは現場で培われた
第六回 9月19日(日)(仮) 近代化と現在:建築基準法の規定する木造工法
(在来工法)の生まれた経緯
会場 東京芸術大学美術学部中央棟2階第3講義室
講師 下山眞司(筑波建築設計代表・筑波大学名誉教授)
募集人数 60名程度
参加費
会員 18,000円、 非会員 21,000円、 学生 12,000円
お問い合わせ・お申し込み
特定非営利法人伝統木構造の会事務局
東京都渋谷区代々木2-36-6 TEL:03-3370-8528 FAX:03-3375-8447
受講申込は添付のPDFの用紙をお使いください。
まだ若干の空席がございます。お申し込みはお早めに!
講習会「伝統を語るまえに・・・・知っておきたい日本の木造建築工法の展開」のご案内をダウンロード
「秩父の山の木で建てる伝統構法の家」建方見学会&研修セミナー
「秩父の山の木で建てる伝統構法の家」建方見学会&研修セミナー
〈日本の森林と伝統建築文化の危機を考える〉
開催日時:平成22年4月24日(土)
集合場所 午前10:50 西武池袋線「西武秩父駅」改札口
集合
主催:本会・住宅研究会
参加申込書 ■参加費500円 (保険料込) ■資料代500円(希望者のみ)
参加申込み締切り:平成22年4月15日(木)
○Y邸プロジェクト建て方現場見学会(約1時間) 見学
○ 研修セミナー「日本の森林と伝統建築文化の危機を考える」
「秩父地域地場産業振興センター5階研修室」
お申込みは fax 03–5834–8605
担当:鈴木まで
※先着順となります ※雨天決行
WEB用4.24秩父をダウンロード
22.3.23